顧客満足度(CS)とは?調査方法や向上させる方法、成功事例を解説!
.jpg?length=80&name=IMG_2166%20(6).jpg)
武田龍哉
2025.08.04

「自社の商品やサービスにお客様は満足しているのか?」と多くの企業が気になるのではないでしょうか?これを把握する際に役立つ指標が「顧客満足度」です。
顧客満足度は、お客様がサービスや商品にどれだけ満足しているかを示すもの。満足度が高ければリピートや紹介にもつながり企業の成長にも直結します。重要な指標のため、意味を理解しておきましょう。
今回は顧客満足度についてわかりやすくご紹介します。顧客満足度を向上させる方法や成功事例までまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
顧客満足度(CS)とは?

顧客満足度(Customer Satisfaction:CS)とは、自社の商品やサービスに対して顧客がどの程度満足しているかを数値化した指標です。カスタマーサクセスやマーケティングの分野で活用されています。
顧客満足度が高い場合は商品やサービスをリピートしてもらいやすくなり、顧客満足度が低い場合は解約リスクが高まりやすくなります。
顧客満足度を左右する要素が期待値です。顧客が購入前に抱いていた期待を上回れば、顧客満足度は高くなります。逆に期待を下回れば顧客満足度が低下します。そのため、顧客満足度を高めるには、顧客の期待を理解し、それを超える価値を提供することが大切です。
顧客満足度(CS)と従業員満足度(ES)の違い
顧客満足度と比較される指標として従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)があります。
従業員満足度とは、従業員が職場にどの程度満足しているかを示す指標です。従業員満足度が高い組織では、従業員のモチベーション高く、顧客対応力や生産性に好影響をもたらします。その結果、顧客満足度の向上にもつながります。
もし、顧客満足度を高めるために取り組んでいるにも関わらず、期待する成果が得られていない場合は従業員満足度に問題ないかを見直してみると良いでしょう。
顧客満足度(CS)を向上させる目的
顧客満足度(CS)を向上させる目的は5つあります。
ブランディングを強化する
顧客満足度を向上させることで、企業が意図しない形で口コミ・評判が自然に広がるようになり宣伝効果が見込めるようになります。
これらにより、消費者の間で会社の認知度が上がり企業の社会的信用も高まります。つまり顧客満足度を向上させる取り組みにより、ブランディングを強化することが可能です。
LTVを向上する
顧客満足度の高い商品やサービスは再購入につながりやすく、リピーター顧客の獲得により売上が安定するようになります。つまり、LTV(顧客生涯価値)が向上します。
近年では、サブスクリプション型ビジネスが増えており、顧客満足の高さがその成否を左右します。リピーターは新規顧客に比べて獲得コストが低いため、リピーター施策は費用対効果の高い戦略といえるでしょう。
関連記事:『LTVとは?意味や計算式、向上させるための施策まで徹底解説!』
新規顧客の獲得
顧客満足度の向上は、新規顧客の獲得にも大きく寄与します。なぜなら、商品やサービスで満足した顧客は平均9人に良い口コミを広めると言われているためです。
このような好循環により、広告に依存せずとも自然な形で新たな顧客層の獲得が可能になります。そのため、顧客の期待を上回る価値を提供し続けてブランド力を高めていきましょう。
コストを削減する
顧客満足度の向上はコスト削減の観点からも大きなメリットをもたらします。顧客満足度が高い企業は、割引やキャンペーンに依存せずとも顧客を獲得でき、広告費を抑えることができます。
また、口コミによる拡散により、新規顧客獲得にかかるコストも削減することが可能です。さらに、社会的評価も上がるため優秀な人材の確保にかかるコストの軽減にもつながります。
他社と差別化を図る
顧客満足度の向上は、競合他社との差別化にも直結します。満足度調査の結果を分析することで、自社の強みと弱点が明確になり差別化戦略を練ることが可能です。
自社の強みを的確に訴求できれば、類似商品・サービスとの単純な価格競争を回避でき、ブランドとしての独自性を確立できます。
また、顧客のニーズに的確に応えることで、多少価格が高くても選ばれる可能性が高まるようになります。そのため、顧客に他社と自社の満足度を尋ねてみましょう。
顧客満足度(CS)を評価する指標
顧客満足度(CS)を評価するための指標には「NPS」「CSI」「JCSI」「CES」があります。他者と自社を比較する際にも役立つ指標のため覚えておきましょう。
NPS
NPS(Net Promoter Score)は、顧客が商品やサービスにどれだけ愛着や信頼を持ち、他人に推薦したいと思っているかを数値化する指標です。
主に「この商品・サービスを友人や同僚にどの程度勧めたいか」という設問に対し、0〜10点で評価を行ってもらい、そのスコアから顧客ロイヤルティを測定します。
結果を推奨者(9〜10点)、中立者(7〜8点)、批判者(0〜6点)の3段階に分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値がNPSです。
この手法により、顧客満足度に加えて、将来的な再購入や紹介の可能性といった「忠誠度」を可視化し、企業の改善施策や成長戦略に役立てることができます。
CSI
CSI(Customer Satisfaction Index)は、顧客満足度を数値化するための指標です。
商品やサービスの購入前に顧客が抱いていた期待と、実際に利用した後に得られた価値とのギャップを可視化するものです。
この指標は、顧客期待値、満足度、忠実度、不満度といった複数の観点から測定され、企業が提供する価値が顧客の期待にどれだけ応えられているかを分析する際に用いられます。
CSIは、単なる「満足かどうか」だけでなく、その背景にある心理的要因や、将来的な購買・継続利用の可能性を読み取るヒントにもなります。
関連記事:『顧客満足度指数CSIとは?調査方法や評価方法、ポイントまで解説』
JCSI
JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)は、国際的に用いられているCSI(Customer Satisfaction Index)を日本市場向けに最適化した顧客満足度の測定モデルです。
従来のCSIが採用していた5つの測定項目(顧客期待、知覚品質、知覚価値、顧客満足、顧客忠誠)に加え、日本独自の指標として「推奨意向」を6番目の項目として追加しています。
JCSIは、より多角的かつ実態に即した顧客満足度分析を可能とし、企業のサービス改善や競争力強化に向けた戦略立案に活用されています。
関連記事:『顧客満足度指数のJCSIとは?レポート活用方法と指標の見方をご紹介』
CES
CES(Customer Effort Score)は、顧客がサービスを利用する際に「どれだけ手間を感じたか」を数値化する指標です。
主にカスタマーサポートやカスタマーサクセスの分野で活用され、問い合わせ対応がスムーズだったか、問題解決までの負担が少なかったかといった観点で顧客の体験を測定します。
一般的には、「サービスを利用して目的を達成するために、どの程度の労力がかかりましたか?」という質問に対し、5段階または7段階で評価してもらいます。
CESは、顧客がストレスなくサービスを利用できるかどうかを示すものであり、満足度や再利用意向に大きな影響を与える要素として注目され始めてきました。
顧客満足度(CS)調査方法の手順
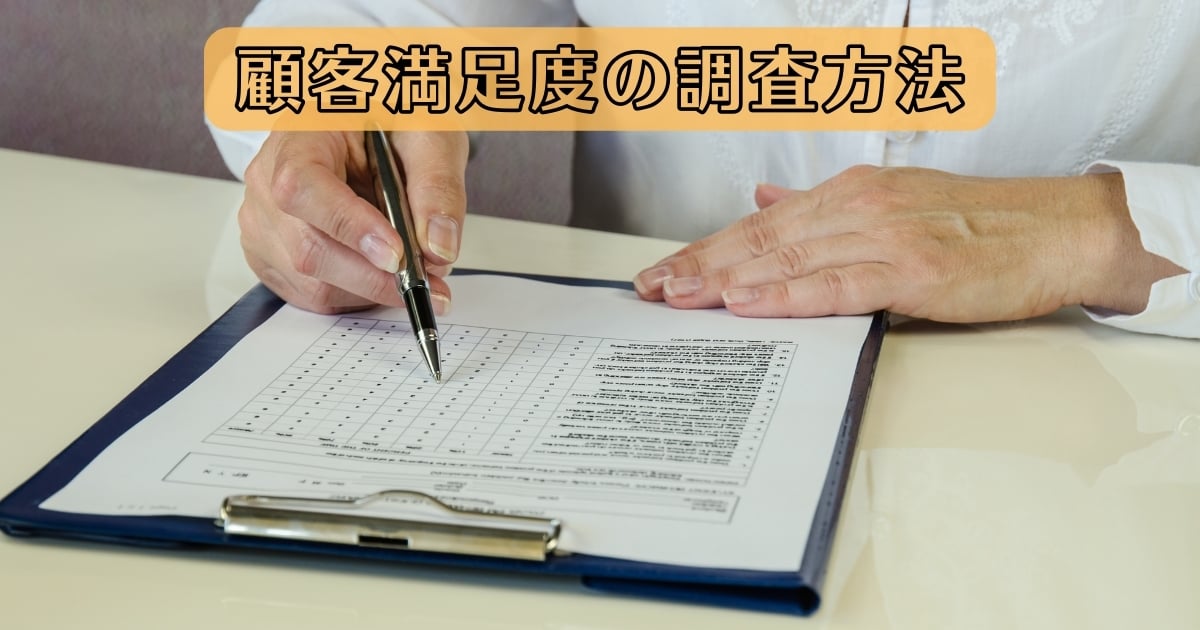
顧客満足度(CS)は8STEPで調査します。
1.目的を定める
まず、顧客満足度調査の目的を定めます。その際にKPI(LTV・リピート率・チャーンレート・リテンションレート・顧客紹介数)を設定しておくことで、KPIを設定しておくことで調査や改善施策の方向性がブレにくくなります。
また、仮説立てしておくことも大切です。例えば「リピート率が低下している」という課題を抱えている場合は「競合他社に流れているのではないか」「サービスの品質が価格に見合っていないのでは」と仮説を立てておくことで社内の認識と実態の差がわかるようになります。
2.調査対象を決める
次に顧客満足度調査の対象を決めます。サービス利用者全体を対象とするのか、特定の条件を満たすサービス利用者に絞るかにより得られる回答が大きく変わります。
例えば、初回サービス利用時に顧客満足度が低下する原因を知りたい場合は、最近サービスを利用し始めたユーザーに調査を行うのが適切です。調査対象により、得られる情報が変わるため、慎重に判断するようにしましょう。
3.調査時期を決める
次に顧客満足度調査の時期を決めます。なぜなら、調査のタイミングにより得られる回答が変わることがあるためです。
例えば、オンライン学習サービスに関するアンケートであれば、新学期の始まりにあたる4月や9月、あるいは試験前などに調査することで、具体的なフィードバックが得られやすくなります。一方で夏季休暇などサービス利用者が少ない時期では、回答数が少なかったり偏りが生じてしまいやすくなります。
このように時期も重要なため、いつ調査を行うか慎重に決めましょう。
4.調査方法を決める
次に調査方法を決めます。目的に応じて適切な調査手法を選ぶことが大切です。ここでは主な3つの方法を紹介します。
(1)インターネット調査
レビューサイトの評価、SNS上での言及などをチェックすることで、ユーザーの印象や関心の傾向を読み取ることができます。「どんな人が」「どんな場面で使用していて」「どのような印象を抱いているか」といった情報は、仮説立ての際に役立ちます。
(2)アンケート調査
アンケートフォームやアンケート用紙を用いて実施する調査方法です。アンケート調査項目を自由に決められるため、さまざまな情報を収集することができます。コストを抑えながら回答を集められ集計や分析も容易なため、あらゆる場面で活用されています。
関連記事:顧客満足度アンケート調査とは?リサーチや分析方法まで徹底解説!
(3)インタビュー調査
顧客に直接話を聞く、インタビュー形式の調査です。1対1での面談や、複数名による座談会(グループインタビュー)など、目的に応じて形式を選ぶことができます。口コミやアンケートでは見えにくい、より深い顧客の感情や行動背景を理解することができます。
CS専門会社アディッシュのユーザーインタビューサービスはコチラ >
5.設問設計を行う
顧客満足度調査方法を決めたら設問を設計します。以下は代表的な設問例です。
| 設問カテゴリ | 設問内容 |
| 顧客満足度を測定する設問 | Q. あなたは○○についてどの程度満足していますか? |
| サービス推奨度を測定する設問 | Q. ○○を家族や友人にすすめたいと思いますか? |
| 満足度の理由を尋ねる設問 | Q. 満足度点数の理由を教えてください |
| 顧客属性を確認する設問 | Q. 年齢を教えてください/サービスを知ったきっかけは何ですか? |
| 継続利用の意向を問う設問 | Q. 今後も○○を利用し続けたいと思いますか? |
6.調査を実施する
顧客満足度アンケートを実施する際は「目的」「所要時間」「回答方法」などを明記した案内文を添えることで、回答者の理解と協力が得やすくなります。また、回答率の向上を目指して、謝礼やインセンティブの導入を検討するのも有効な手段です。
調査手法によって留意点は異なりますが、Webアンケートの場合は、リマインドメールの送信や回答状況のモニタリングを行い、進捗を把握しながら対応するなどの工夫が大切です。
7.調査結果を分析する
アンケート調査が完了したら、自社の課題を明らかにするための分析を行います。目的に応じて分析手法を使い分けましょう。
(1) 単純集計
設問ごとの回答数や割合を集計する、最も基本的な分析方法です。顧客全体の傾向や満足度の平均値、選択肢ごとの分布などを把握するのに適しています。
(2) クロス集計
複数の設問項目を掛け合わせて分析する方法です。たとえば、「年齢層」と「満足度」をクロスして集計することで、どの年代の顧客がより満足しているかなど、属性ごとの傾向を明確にできます。より深いインサイトを得たいときに有効です。
(3) ポートフォリオ分析
「重要度」と「満足度」の2軸で複数の評価項目をマッピングし、改善の優先順位を可視化する手法です。顧客満足度を高めるために、どの項目に注力すべきかを明確にし、戦略的な改善計画の立案に役立ちます。
8.報告書にまとめる
アンケート調査の結果は、社内の関係者全員が理解し、活用できるように報告書として整理しておくことが重要です。明確で実用的な報告書を作成することで、調査結果をもとに具体的なアクションにつなげやすくなります。
<報告書に記載すべき主な内容>
- 調査の目的
- 調査の背景
- 調査の概要
- 調査結果のサマリー
- 今後のアクション
顧客満足度を向上させる方法

顧客満足度を調査したら、回答を参考にしながら改善することが大切です。ここでは、顧客満足度を向上させる取り組みをご紹介します。
具体的な顧客満足度を上げる具体例は下記の記事にて詳細に解説しておりますので、こちらもご覧ください。
参考記事:顧客満足度を上げる具体例10選!成功企業の事例とともに解説
顧客の声を把握して改善する
顧客満足度を高めるためには、顧客がどのような期待や不満を持っているのかを正しく把握することが欠かせません。その第一歩が「顧客の声」に耳を傾けることです。
サービスの改善点など把握して改善すれば、顧客満足度を向上させることができます。
関連記事:VoC分析とは何か?収集方法や分析方法、手順を解説!
サービスコンセプトを明確にする
自社が提供する商品の価値が正しく伝わっていれば顧客満足度は自然と高まります。そのため、サービスコンセプトを明確にしておきましょう。
サービスコンセプトとは、「誰に、何を、どのように届けるのか」を端的に示すもので、企業が提供する価値の核となるものです。
サービスコンセプトを明確にすることで、ミスマッチを防ぎ、納得感のある利用体験を提供できるようになります。
競合商品と差別化を図る
顧客満足度を高めるためには、自社商品が競合商品よりも魅力的であることが大切です。そのために、他社との違いをつくり価値を打ち出しましょう。
価格や機能など表面的な要素だけでなく「使いやすさ」「サポート対応」「ブランドの信頼感」「体験価値」などで差別化するのも効果的です。魅力的な商品を作れば顧客ロイヤルティを向上させられます。
オペレーションを最適化させる
顧客満足度を向上させるためには、日々の業務フローや対応プロセスなど、オペレーションの最適化が欠かせません。どれほど優れた商品やサービスを提供していても、対応の遅れや不備、煩雑な手続きがあると、顧客の不満につながってしまいます。
たとえば、注文から納品までのスピード、問い合わせへのレスポンス時間、キャンセルや返品時の対応手順など顧客と接点を持つ各プロセスがスムーズであることが大切です。
オペレーションの改善は、顧客体験の安定性・一貫性を高めると同時に、従業員の負荷軽減や業務品質の向上にもつながります。これにより、組織全体としてのサービスレベルの底上げが期待できます。
ITツールを導入する
顧客満足度を効率的かつ継続的に向上させるためには、ITツールの導入が有効です。
例えば、CRM(顧客管理システム)を導入すれば、顧客の属性や購買履歴、問い合わせ履歴などを一元管理でき、個別ニーズに応じた対応がしやすくなります。
これにより、「一人ひとりに合ったサービス」を提供することが可能となり満足度向上に直結します。このようなITツールを上手く活用するようにしましょう。
従業員満足度を向上する
従業員が現在の職場環境に満足できていないと、十分なパフォーマンスを発揮することができません。
商品や顧客関係を改善するための優れたプランを考えられなかったり、顧客とのコミュニケーションのあり方がずさんになったりするからです。
このような事態に悩まされている場合、まずは従業員満足度の改善から取り組んでみるのが良いでしょう。
参考記事: 従業員満足度(ES)とは?向上させるメリットと取り組み方法を解説!
顧客満足度の改善事例
顧客満足度の改善は、すでに多くの企業で取り組まれています。ここでは主な3つの事例を紹介します。
ソニー損害保険株式会社

出典:『ソニー損害保険株式会社』
ソニー損害保険株式会社は、JCSI調査において4年連続で顧客満足度第1位を獲得するなど、高い評価を受けている保険会社です。顧客満足度向上に向けた同社の取り組みの特徴は、「先回り」の対応にあります。
顧客が不安やリスクを感じる前に、必要なサポートを提供する姿勢を徹底しています。具体的には、24時間体制の事故対応サービスに加え、外国語通訳サービスの提供など、多様な利用者に配慮した支援体制を整備。これにより、保険利用時の不安を大幅に軽減し、安心してサービスを利用できる環境を構築しています。顧客一人ひとりに寄り添う丁寧な対応が、継続的な信頼と高い満足度の獲得につながっています。
GMOメイクショップ株式会社
ECサイト構築サービスを提供するGMOメイクショップ株式会社は顧客情報の一元管理を実現し、売上192%増を達成するとともに、顧客満足度の向上にも成功しました。
以前は部門で異なるツールを使用しており、情報共有に時間と労力がかかっていたため、迅速で的確な対応が難しい状況にありました。そこで全社で共通のツールを導入し、顧客情報を一元化しサポート体制の質が大幅に向上しました。
これにより、顧客一人ひとりに対してスムーズかつ丁寧な対応ができるようになり、顧客満足度の改善に成功しました。
株式会社日立ハイテクサイエンス
日立グループの分析機器メーカーである株式会社日立ハイテクアナリシスは、顧客満足度を可視化するために調査ツールを導入し、継続的に商品・サービスを改善する体制を構築しました。
満足度調査の設問設計や回答データの分析が効率化でき、問題を洗い出せるツールを導入することで、顧客満足度の向上の両立に成功しました。最も使いやすいツールを選ぶことで、運用負担を抑えたこともポイントです。
まとめ
顧客満足度(CS)は、商品・サービスに対する顧客の期待値が、購入後・契約後にどのくらい満たされたか数値化する指標です。
顧客満足度が高ければ、売上の維持・拡大やブランディングなどの効果も見込めるため、企業の成長につなげられます。
顧客満足度を向上させるには、一人ひとりのスキルアップだけでなく、カスタマーサクセスの強化やツールの導入など組織一丸となり取り組む必要があります。
アディッシュ株式会社は、カスタマーサクセスの構築支援やコンサルティング、研修など、カスタマーサクセスをはじめとする顧客対応部門の強化を総合的に支援しています。
これから始めたい方、すでに始めていて効果が出ていない方、さらに強化したい方など、事業の規模や目的に応じて柔軟にサポートさせていただくので、ぜひ一度ご相談ください。
.jpg?length=160&name=IMG_2166%20(6).jpg)
この記事を書いたライター
武田龍哉
Web制作会社、広告代理店を経験後、アディッシュに入社。 マーケティング担当としてリード獲得やナーチャリングの施策立案、実行を担当した後、インサイドセールスチームへ参画。 インサイドセールスチームでは、主にカスタマーサクセスの関連商材を担当し、商談機会創出とチーム体制構築に携わる。




