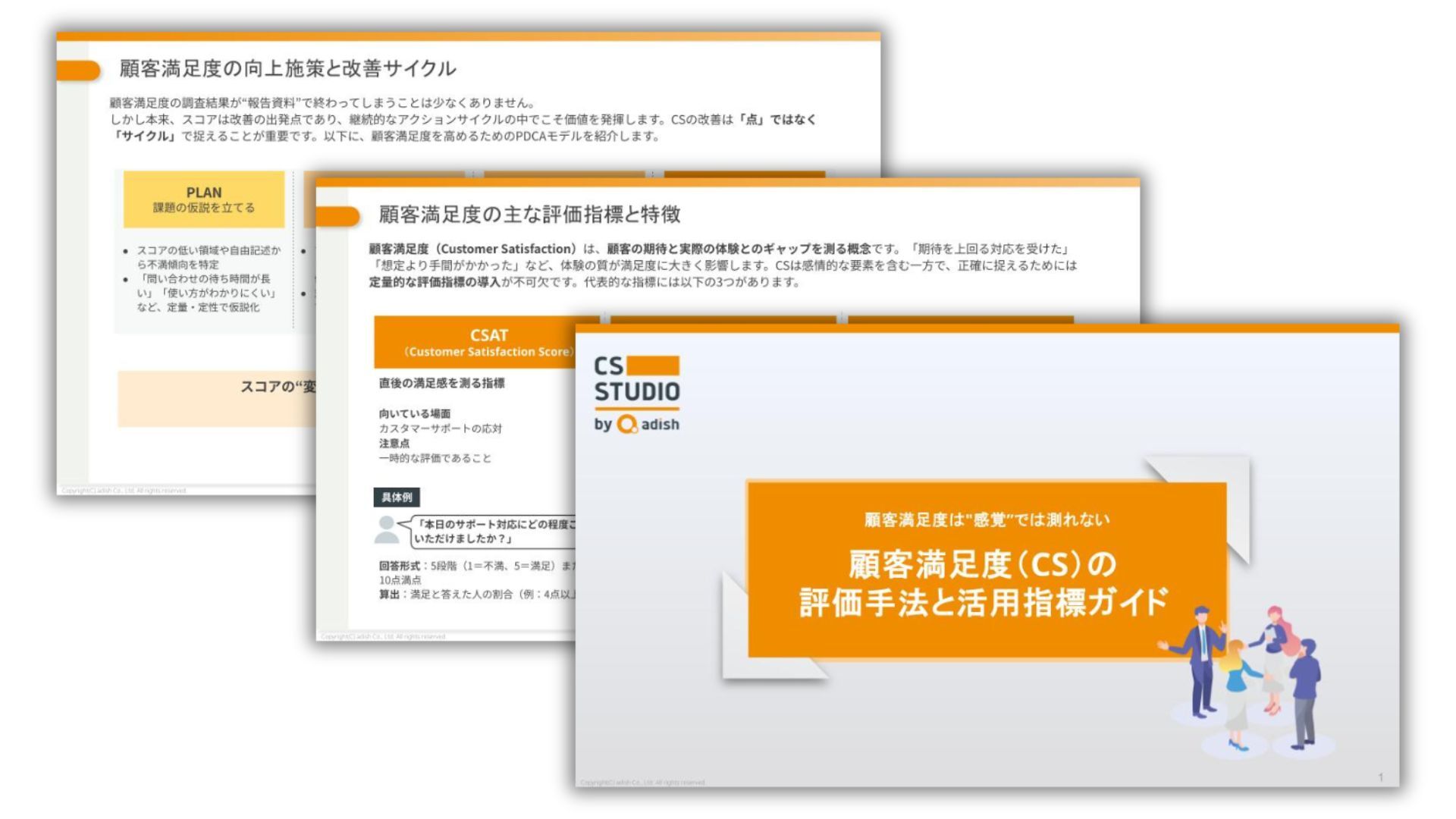NPSとは?顧客満足度との違いや算出方法について解説
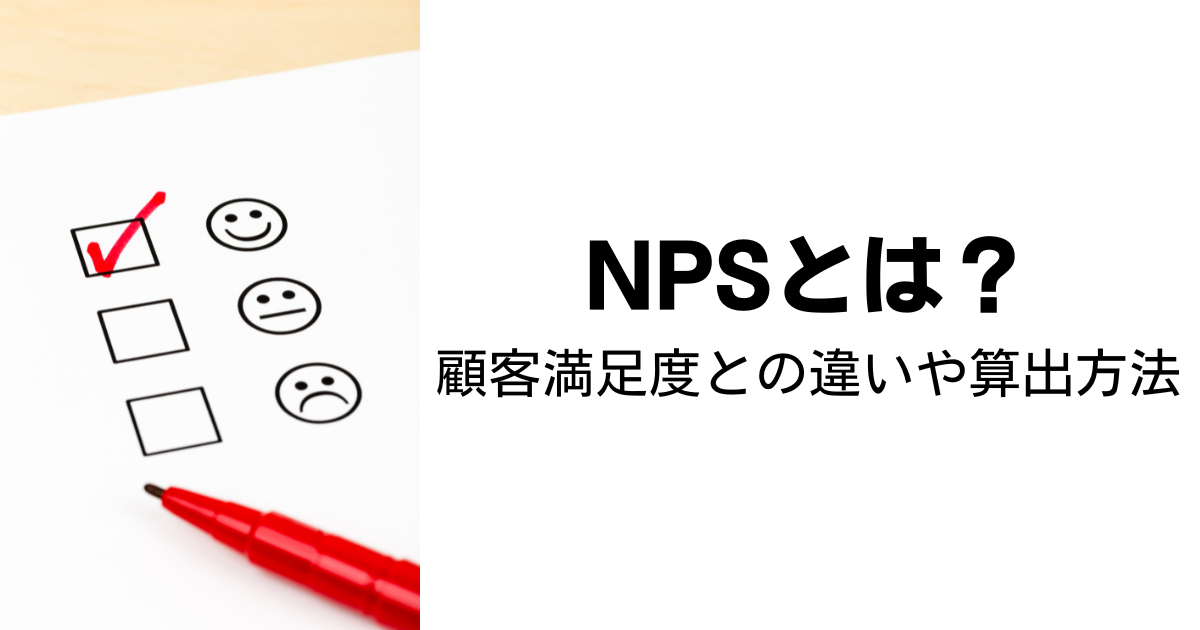
事業を成長させていくためには、顧客ロイヤリティを向上させていく必要があります。そのため、NPSアンケート調査を実施する企業が増えてきましたが、なぜNPSスコアが注目されているのでしょうか?どうすればスコアは向上するのでしょうか?
今回はNPSについて詳しく解説します。この記事を読めば、NPS調査の重要性や実施方法が理解できるようになるため、導入を検討している方は読んでみてください。
NPS(ネットプロモータースコア)とは

NPS(ネットプロモータースコア)は顧客ロイヤリティを測定するための指標です。顧客が商品やサービスにどれぐらい信頼を寄せてくれているか、家族や友人に勧めてくれる可能性があるかを把握するためにスコア調査します。
2003年に米国大手コンサルティング会社ベイン・アンドカンパニーが考案し、同国の売上上位1,000社の3分の2の企業にてNPS調査が実施されています。
多くの企業が導入する理由は、顧客ロイヤリティが高ければリピート回数や顧客単価が向上したり、家族や友人に商品を薦めてくれるようになるためです。また、SNS上での情報拡散も期待できるでしょう。このような効果が期待できることから、顧客ロイヤリティを測定するためにNPS調査の導入が進んでいます。
関連記事:『顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティを高める施策や成功事例を紹介!』
NPSと売上の相関関係
NPSスコアは売上高成長率と高い相関関係であることが明らかになっています。NPSスコアが高いユーザーの方は商品の購入率、推奨度が高いことが判明しているのです。
またNPSスコアが高い企業(ロイヤルティ・リーター)は競合他社の2倍の売上高成長率を遂げていることも判明しています。つまり、NPSスコアを向上させると大きな経済価値を生み出すことができます。
NPS調査の重要性

NPS調査は顧客の声を聞き、商品やサービスを改善し事業成長を促すために必要なものです。ここでは、NPS調査の重要性について解説します。
顧客の声を収集できる
NPS調査シートに自由回答欄を設けておけば「なぜ、そのような評価をしたのか?」を聞くことができます。ポジティブな意見は自社の強みと捉えてプロモーションなどに活かすことで、新規顧客を獲得しやすくなるでしょう。
一方で、ネガティブな意見は自社の弱みと捉え改善していくことが大切です。顧客の声を真摯に聞く企業と印象を与えることができ、良い関係を築くことができます。このように、自社の商品・サービスに対する顧客の声を聞くためにNPS調査に取り組む企業が増えました。
商品・サービスの改善に役立てられる
顧客の声を収集すれば、商品・サービスの改善に役立てられるようになります。「このようなオプションサービスがあれば便利なのに」「サービスを利用する際に不便だった」などの意見を取り入れて、商品・サービスを改善していけば、モノが溢れる市場でも選ばれやすくなります。なぜなら、顧客ニーズを満たした商品、サービスが提供できるようになるためです。
また、さまざまな企業がNPS調査を行っています。業界平均値スコアも公表されているため、自社スコアと比較すれば市場での競争力がどれぐらいであるかを把握することができます。
事業成長を促せる
繰り返しになりますが、NPSスコアは売上高成長率と高い相関関係があります。なぜなら、NPSスコアが高いことは、顧客ロイヤリティが高いことでもあり、リピートして商品を購入してもらえたり、家族や友人に商品を薦めてもらえたりしやすくなるためです。
業界においてNPSスコアが高い企業(ロイヤルティ・リーダー)は競合他社の2倍の売上高成長率を遂げていることも判明しているため、今後成長の余地があるか把握したい際にもNPS調査をおすすめします。
NPS調査の導入ステップ

NPSは7STEPで導入できます。
1.NPS調査の目的を定める
まず、NPS調査の目的を定めます。なぜなら、目的が曖昧なままではNPSスコアを測定して満足してしまい改善に役立てられなくなるためです。
また、NPS調査の目的次第で「いつ」「誰に」「どのように」調査するかも変わります。よくあるNPS調査の目的を載せたので参考にしながら、ぜひ最初に考えてみてください。
<NPS調査の目的>
- 顧客ロイヤルティがどれぐらいかを把握したい
- 解約リスクを早期に発見したい
- カスタマーサクセスのKPIとして設定したい
- 顧客視点を参考にしながら経営の意思決定をしたい
2.NPS調査対象を決める
次にNPS調査対象を決めます。誰に調査するかで得られるインサイドは変わるため慎重に選びましょう。
| 対象者 | NPS調査目的 |
| 全顧客 | NPSスコアの全体傾向の把握 顧客ロイヤリティの把握 |
| 直近でサービスを利用した顧客 | サービス体験者としての評価 サービス改善案の収集 |
| カスタマーサポートを利用した顧客 | サポート品質の評価 |
| 業種や契約年数別 | セグメント別の特徴の把握 |
3.NPS調査シートを作成する
次にNPS調査シートを作成します。
調査シートは設問内容や設問数を工夫することが大切です。
NPS調査の回答が5分以内にできるように、7問以内に抑えるのが理想です。そのため、必要最低限の数に項目を絞り込みましょう。
また、11段階のNPSスコアを測定するものですが、スコアだけでは顧客心理は把握できません。顧客心理を把握するためにも「その点数をつけた理由をお聞かせください」と自由記述欄を設けておきましょう。
4.NPS調査を実施する
次にNPS調査を実施します。調査対象者に調査する際に、いつどのように調査すべきか判断しましょう。
例えば、商品やサービスに関するフィードバック収集が目的の場合は、サービス体験後のお客様にNPS調査をすると貴重な意見を収集しやすくなります。
また、サービス利用開始直後のお客様にNPS調査をすると、オンボーディングが理解しやすかったかどうかを把握できます。併せて、調査対象者にとってオフラインとオンラインのどちらが回答しやすいかも考慮して、NPS調査を実施しましょう。
5.NPSスコアを計算する
次にNPSスコアを計算します。
「あなたは●●を友人や知人にどの程度すすめたいと思いますか?」と10点で評価してもらい
- 「0~6点:批判者」
- 「7~8点:中立者」
- 「9~10点:推奨者」
に分類します。そして「推奨者の割合(%)-批判者の割合(%)=NPSスコア」で算出します。
6.フィードバック分析する
次にフィードバック分析を行います。
自社のNPSスコアが業界水準と比較してどうなのかを調べることで、事業成長の余地を把握できます。
・業界別NPSの平均値
| 自動車 | -18.5ポイント |
| 情報通信・インターネット | -36ポイント |
| 資源・エネルギー・素材 | -53ポイント |
| 金融・法人サービス | -45ポイント |
| 食品 | -15ポイント |
| 衣類 | -20ポイント |
| 旅行 | -15ポイント |
| 医療・製薬 | -15ポイント |
| 人材 | -35ポイント |
| 生活・公共サービス | -45ポイント |
また、顧客の意見をポジティブとネガティブに分けて、頻出する順に並べておくことで商品・サービスの改善、プロモーションに活かせるようになります。
7.NPSスコアを改善する
最後にNPS調査結果を参考にしながら、どうすればNPSスコアを改善できるか施策を検討して行動に移していきます。
NPSスコアの改善とは、顧客との関係性を深め、ブランドへの信頼を築くことためのものです。そのため、顧客の声を参考に改善していき、スコア改善を図るといった循環を止めずに回し続けましょう。
NPSスコアを改善するコツ

NPSは売上成長率と相関関係があるため、向上させていきましょう。ここでは、NPSスコアを向上させるコツをご紹介します。
社内全体でNPSスコアを共有して意識改革を行う
NPSスコアを向上させるためには、より良い顧客体験を提供できるように全社で取り組まなければなりません。社内全体でNPSスコアを共有して意識改革と行動へつなげる必要があります。
そのため、定例会でNPS調査結果を共有して状況や印象的なコメントを共有しましょう。
また、担当者の対応がよかったとコメントがあった場合は表彰するなど称えて、今後も積極的に取り組んでもらえるようにします。
商品やサービスを改善する
NPS調査で収集したスコアとコメントを活かして、商品やサービスを改善することも大切です。
「操作性」「サポート対応」「機能の充実度」「導入時のスムーズさ」「価格」のどの項目がスコアを下げているのか分析しネガティブなコメントから改善策を考えます。
例えば、UI/UXに関する不満が多い場合は、操作マニュアルの見直しやオンボーディング強化がおすすめです。またサポートに関する不満が多い場合はチャットボットやFAQの整備、応対品質の標準化をするとよいでしょう。
顧客に対策に講じたことを報告する
商品やサービスの改善を行った後に、メールやニュースレター、個別連絡で顧客に報告するようにしましょう。なぜなら、顧客にとって「自分の声が商品やサービスの改善につながった」と実感できればエンゲージメントが高まるためです。
「声が届いている」と信頼してもらいやすくなり、顧客ロイヤリティが向上します。次のNPS調査にも協力してもらえるようになります。
NPS調査を継続的に実施して改善できているかを把握する
NPS調査は一度きりで満足せず、継続的に実施しましょう。NPSがどれくらい良いかよりも、前回よりどう変化したかが重要です。
NPSスコアの推移やコメントの変化を確認することで、改善施策の効果を把握できます。そのため、四半期に1回、半年に1回はNPS調査を実施するなど定期的なサイクルとして組み込んでおきましょう。
NPS調査の活用事例

NPSアンケート調査のやり方をご紹介しましたが、実施している企業では、どのような効果が見込めているのでしょうか?ここでは、NPSアンケート調査の活用事例をご紹介します。
飲食店
A社は首都圏を中心に店舗展開している「食べるスープ」の専門店です。従来のスープとは異なり、主食として満足感のあるボリュームと栄養バランスを重視したメニューを提供しています。顧客一人ひとりの声を丁寧に汲み取り、定期的なアンケートやSNSのフィードバックを通じて、商品改良や新メニュー開発に反映させています。
近年は実店舗だけでなく、オンライン販売(EC)にも注力。人気メニューを家庭でも楽しめるよう冷凍商品として展開しています。こうした顧客中心のアプローチが功を奏し、NPS(ネット・プロモーター・スコア)も高水準を維持しており、リピーターの増加や来店頻度の向上につながっています。
小売店
B社は、10代から30代の女性を主なターゲットとするレディースインナーのブランドです。ファッション性と快適さを両立させた商品展開が特徴で、全国の実店舗を中心に販売しています。
同社ではこれまで、店頭での接客を通じて顧客にブランドイメージについての質問を行ってきましたが、定性的で評価に活用しにくいという課題を抱えていました。この課題を解決するために、B社はNPS(ネット・プロモーター・スコア)調査を導入し、顧客満足度やブランドへの推奨度を数値として可視化できるようにしました。
これにより、顧客体験のどこに問題があるのか特定できて、より良いサービスを提供できるようになりました。
住宅会社
C社は注文住宅会社で、これまで住宅の引き渡し後に顧客アンケートを実施し、満足度の把握に努めてきました。しかし、アンケートでは自由記述が多く、お客様の声を共有する仕組みも整っておらず、業務改善に活かせていないという課題を抱えていました。
こうした背景から、NPS調査の導入を決定しました。NPS調査により顧客満足度をスコアとして把握できるだけでなく、「なぜその評価をしたのか」といった理由を深掘りする設問を通じて、より具体的で業務改善に活かしやすいフィードバックを得ることが可能になりました。
まとめ
NPSは顧客ロイヤリティの指標となるものです。顧客ロイヤリティが高ければ、「リピート率向上」「顧客単価の向上」「情報拡散」などの効果が見込めて売上も伸びていきます。
米国の売上上位企業(Fortune1000)の3分の2がNPSを採用していることでも有名です。この記事では、NPS調査の手順やNPSスコアを向上させる方法をご紹介しました。これを機会に、ぜひNPS調査を実施してみてください。
顧客満足度向上につながるCS支援