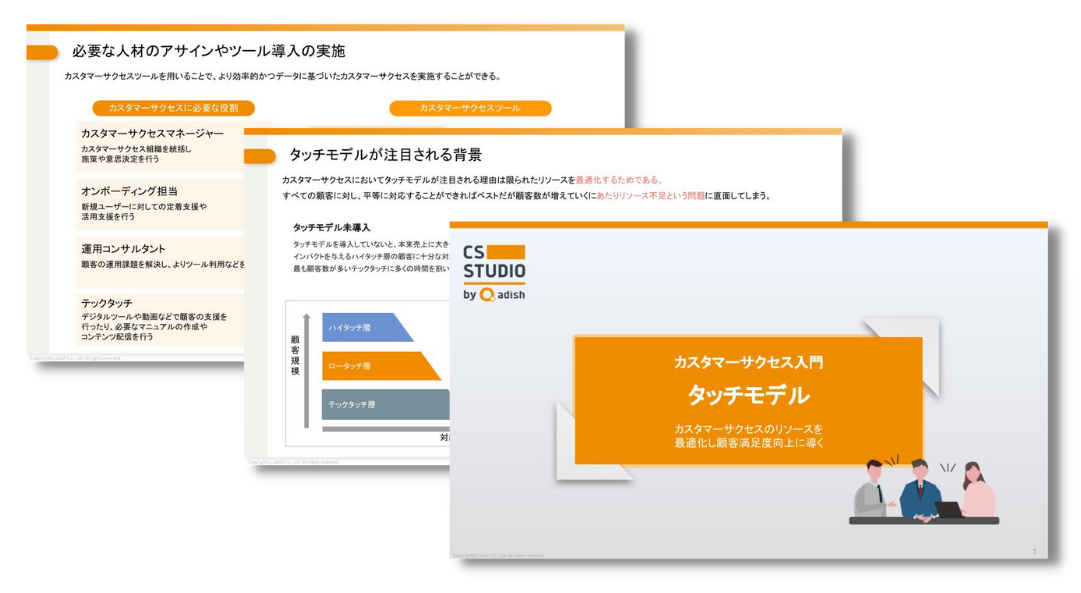顧客接点はデジタル化が必須?6つの具体策と事例を紹介

山田理絵
2024.10.15
顧客接点(タッチポイント)とは、企業が顧客と接する場所や手段のことです。
従来、顧客接点はマーケティング分野において重視されてきましたが、近年ではビジネス全般に必要な考え方として広まりつつあります。特に昨今はデジタル技術の進展が著しく、顧客接点のデジタル化が急務だといえます。
しかし、デジタル接点を強化しようにも、「なかなか周りの協力が得られない」、「どのような手段を用いれば良いのかわからない」と悩む方も多いでしょう。
顧客接点をデジタル化する具体策を理解しておけば、関係者と交渉しやすくなる他、顧客ニーズに合う適切な施策を考案できます。
本記事では、顧客接点をデジタル化する重要性や具体策を詳しく解説します。企業の成功事例も紹介していますので、デジタル接点のイメージを深めながら具体的な施策を考案できるでしょう。
そもそも顧客接点とは?を詳しく知りたい方は下記の記事も確認
顧客接点をデジタル化する重要性
まずは、顧客接点をデジタル化する重要性をご紹介します。
【顧客接点においてデジタル化が重要な理由】
- デジタル接点のニーズが拡大しているため
- 機会損失を防ぐため
- データを有効活用するため
- デジタルカスタマーサクセスにデジタル接点が必要なため
- 営業担当者の人手不足を解消するため
- コストカットにつなげるため
上記の6点は、事業をしていくうえで直面することの多い事項でもあります。
デジタル時代に対応できるよう顧客接点を最適化し、課題解決をはかりましょう。
デジタル接点のニーズが拡大しているため
まず、デジタル接点におけるユーザーのニーズが拡大していることが挙げられます。インターネットやスマートフォンの普及に伴い、デジタル上で顧客と接する機会がますます増えています。
具体的にはWebサイトやSNS、メール・チャット、モバイルアプリなどです。
博報堂の調査によると、1日あたりのメディア接触時間は、2010年から2020年の間にテレビが30分ほど減少しスマートフォンが5倍近く伸びていることがわかりました。
また、最近では、ウィズコロナによりテレワークやICTの活用が加速しています。
このような環境の変化に対応するためには、アナログ接点をデジタル接点に移行したり、デジタル接点を強化したりする必要があるでしょう。
機会損失を防ぐため
機会損失の抑制につながる点も、理由のひとつです。
米国のリサーチ会社CEB Marketing leadership Councilの調査によると、BtoBビジネスにおける購買担当者は、営業担当者に会うまでの間に57%の購買プロセスが完了していることが明らかとなっています。
現代の買い手はBtoBやBtoCに限らず、自分自身で情報収集をして意思決定を行うと言われています。
そんな中、デジタル接点を持っていなければ、購買プロセスにおける情報収集の段階で、自社の存在を認知してもらえないかもしれません。結果、機会損失へとつながってしまう可能性があります。
購買行動の変化により、いまや業界や業種にかかわらず、デジタル接点の維持・拡大が欠かせないといえます。
データを有効活用するため
デジタル接点から得られるデータは、貴重な経営資源です。例えば、開発した商品やサービスが思うように売れない場合、定量的なデータを元にした改善や改良は難しいものです。
デジタル上の顧客接点があれば、常に最新の行動データを収集できるほか、商品やサービスに対するフィードバックを受け取れるでしょう。顧客の行動データを分析・検証し、商品やサービスの品質改善に役立てられます。また、社内でデータ共有を行い業務改善につなげることも可能です。
デジタルカスタマーサクセスにデジタル接点が必要なため
顧客接点のデジタル化は、デジタルカスタマーサクセスを実現するうえでも重要です。慢性的な人手不足のなかで個別の担当者を配置するのが難しい現在では、テクノロジーを駆使して顧客を支援するテックタッチの重要性が高まっています。
テックタッチを最大限に活用するのが、デジタルカスタマーサクセスです。
デジタルカスタマーサクセスを成功に導くためには、デジタル化された顧客体験を最優先に考える必要があります。効果的なカスタマーサクセスの施策を実施するためにも顧客接点のデジタル化は必須です。
営業担当者の人手不足を解消するため
カスタマーサクセス以外に営業やマーケティングの領域でも顧客接点のデジタル化が求められています。
その要因のひとつが営業担当者の人手不足です。
従来、対面営業もしくは、オンライン商談だとしても、1対1でのやり取りが中心でした。しかし、慢性的な人手不足が続くなか、マンパワーに依存する属人的な顧客接点では、効率的な営業活動を行うことはできません。
その解決策の糸口となるのが、顧客接点のデジタル化です。例えば、情報発信を行えるオウンドメディアやSNSといったチャネルは、商品やサービスの魅力を広く伝える営業担当者のような役割を持っています。
デジタル接点をうまく活用することで、慢性的な人手不足にも対処しやすくなるでしょう。
コストカットにつなげるため
顧客接点をデジタル化すると、コストカットにもつながります。デジタル接点における施策は、アナログ接点で発生しがちな多数の無駄を解消できるためです。
例えば、営業担当者を配置する代わりにオウンドメディアやSNSで情報発信を行う場合、新たに人材を採用する際の金銭的コストを大幅に引き下げられます。
ほかにも、商談をすべてWeb会議システムで行うようにすれば、取引先まで出向く時間的コストを抑えられるでしょう。
アナログ接点には信頼関係の築きやすさや柔軟な対応のしやすさといったメリットがあるため、必ずしもデジタル接点ばかりを重視すれば良いというわけではありません。
最適なアナログ接点へとリソースを割けるよう、可能な範囲でデジタル化を実施し、コストカットをはかる必要があるでしょう。
顧客接点のデジタル化を推進する具体策
顧客接点をデジタル化する方法は次の通りです。
- 組織の意識改革
- 組織の構造改革
- マーケティング施策の現状を可視化
- 契約後の顧客応対業務のデジタル化
- カスタマーサクセスのテックタッチ拡充
- データの有効活用
- オムニチャネル戦略
それぞれの具体策を詳しく解説します。
組織の意識改革
顧客接点のデジタル化を進める上で最も重要なのが、組織の意識改革です。マネージャー層がどれだけ優れた施策を考案しても、周りの従業員の意識が低ければ、実行に移すのは困難だからです。
反対にマネージャー層のデジタル化に対する意識が低い場合は、チームメンバーが提案しても却下され、いつまで経っても進展しないといった問題が起こり得ます。
社内のデジタルリテラシーを高めるには、次のような手段が効果的です。
- 抵抗感の少ない部分から徐々にITツールやシステムを導入する
- 社内の各層においてデジタル化の目的や目標を丁寧に説明する
- 社内ルールの見直しを行う
- 従業員のITリテラシーを高める研修を実施する
- 新たなIT人材を確保する
- 外部パートナーと連携する
この方法は顧客接点のデジタル化だけではなく、DXを推進する際にも役立ちます。
組織の構造改革
顧客接点をデジタル化するには、組織の意識改革に加えて構造改革を行うことも重要です。組織のなかで働く従業員の意識だけではなく、構造そのものを変えるには具体的な運用体制を改革する必要があります。
例えば、全社的にデジタルマーケティングを実施できる体制を構築する場合、マーケティング部門だけで実行に移すのは困難です。
そこで、部門を横断したデジタルセンターを構築し、マーケティングや営業、情報システムといった各部門との連携をはかる方法が効果的です。
顧客接点のデジタル化は、組織内の意識だけ変革しても成り立ちません。意識改革とともに、デジタル接点を構築する構造そのものを変えていきましょう。
マーケティング施策の現状を可視化
デジタルマーケティングで顧客接点の強化をはかるなら、現在実施している施策内容を可視化する必要があります。
現状を理解していないと、顧客を支援する新しいソリューションを生み出したり、実現可能なアクションプランを策定したりするのことは困難だからです。
マーケティング施策を可視化するには、横軸に「顧客の購買プロセス」を、縦軸に「マーケティング施策」を配置し、現在利用しているデジタルソリューションをマッピングする方法が有効です。
このような図ができあがると、デジタルマーケティングの全体像を一目で把握できるでしょう。
不足する箇所があれば新たなツールやシステムの導入を検討し、反対に重複している箇所や活用が進んでいないものは廃止を検討するのもひとつの方法です。
契約後の顧客応対業務のデジタル化
マーケティング以外にカスタマーサポートの領域でも、顧客接点のデジタル化が必要です。これまでのカスタマーサポートはコールセンターが一般的でしたが、近年、企業の問い合わせ窓口が多様化しています。
電話以外にも、公式サイトの問い合わせフォームやSNS、メール、チャットなどを活用して顧客応対を行う企業も多いでしょう。
企業とコンタクトをとる顧客がデジタルへとシフトしているため、応対業務のデジタル化は急務だといえます。
顧客のニーズに合わせてデジタルチャネルを拡充することで、場所にかかわらず好きなタイミングでカスタマーサポートを受けられるようになり、CX(顧客体験)の向上へとつながります。
カスタマーサクセスのテックタッチ拡充
カスタマーサクセスを実施する場合、リソースの関係ですべての顧客に手厚い支援を行うことは困難です。
人手を介する必要のない部分のみをテクノロジーで代替する(テックタッチ)ことで、リソースを削減でき、サポート体制がより充実します。
カスタマーサクセスにおけるテックタッチには次のような手段があります。
- サービスの内部にチュートリアルやガイドツアーを実装
- 公式サイトにチャットボットを導入
- よくある質問をまとめたFAQを用意
- マニュアル動画やステップメールを提供
テックタッチで人的リソースを抑えた分、ハイタッチやロータッチといった箇所に人員を集中できます。
データの有効活用
収集したデータを効果的に活用することで、顧客接点のデジタル化を推進しやすくなります。デジタル接点にはWeb広告やオウンドメディア、SNS、モバイルアプリなど多様な種類が存在します。
膨大な数のデジタル接点の中から自社に合うものを見つけるには、顧客の行動データ分析を行うのが効果的です。
例えば、自社のターゲット層がメールを使う機会がほとんどない場合、メールマガジンやステップメールなどのデジタル接点を用意しても効果は見込めないでしょう。
反対にチャットボットやSNSの公式アカウントなどを拡充したほうが、顧客ニーズを的確に捉えられます。
顧客の行動データを収集する方法は次の通りです。
- 会員登録データを集計
- ECサイトの注文履歴を集計
- Googleアナリティクスをはじめとするアクセス解析ツールを使用
- 顧客へのアンケートを実施
- 顧客のSNSへの投稿を分析
- GPSの位置情報を集計
収集したデータを表計算ソフトで管理するほか、事業規模に合わせてCRM(顧客管理システム)やCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)を活用するのも良いでしょう。
オムニチャネル戦略
顧客接点のデジタル化に密接に関わるのが、オムニチャネル戦略の構築です。オムニチャネルとは、デジタルとアナログのすべての販売経路を結び合わせ、総合的に顧客にアプローチする方法です。
デジタル接点とアナログ接点の垣根が存在しないため、顧客はチャネルの違いを意識せずにサービスを利用できます。
オムニチャネルの環境下では、在庫情報をはじめとするオンライン・オフライン間のデータが統合されているのが特徴です。
そのため、店頭で在庫切れが発生しても、ECサイトの在庫から商品を直接発送でき、機会損失を最小限に抑えられます。
しかし、オムニチャネルを構築するためには、オンライン・オフライン間の在庫情報やチャネルごとのブランドイメージを統一しなければならず、環境を整えるまでに多くの時間と労力が必要です。
先にマルチチャネルやクロスチャネルの環境整備から進めることで、スムーズにオムニチャネルへと移行できるでしょう。
マルチチャネル・クロスチャネル・オムニチャネルの違いは下表の通りです。
| 手法 | 特徴 | 施策例 |
| 1. マルチチャネル | オンラインやオフラインに限らず、さまざまなチャネルを展開させる方法 | 実店舗に加えてECサイトを構築 |
| 2. クロスチャネル | マルチチャネルで取り扱うデータを連携させ、1つのシステムで管理する方法 | 実店舗で完売している商品をECサイトの在庫から充当 |
| 3. オムニチャネル | クロスチャネルのデータ統合に加え、チャネルごとのブランドイメージや顧客体験を統一化させる方法 | 実店舗でウィンドウショッピングを行ってもらい、その後ECサイトでの注文に結び付ける導線を設計 |
顧客接点のデジタル化に成功した企業事例
ここでは、顧客接点のデジタル化に成功した4つの企業事例をご紹介します。
トランスコスモス
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供するトランスコスモスは、DX推進の一環として、あらゆる顧客接点をデジタル化する取り組みを行っています。
そのなかで特に力を入れているのがVOC(顧客の声)の活用です。消費者とのコミュニケーションにおいてDXを実現するためには、コールセンターで得られるコールログ・チャットログといった顧客の声と、マーケティング部門で得られるデジタル上の行動ログを統合分析する必要があります。
そこでトランスコスモスでは、コールセンターから得られるVOCを自動抽出し、対応するコンテンツのPVや離脱率のほか、FAQ・チャットボットでの解決率などを可視化しました。
VOCをもとに改善点を特定し施策を実行することで、チャネル個別の最適化に成功しています。
サービス導入から利用促進に向けた導線を整備した結果、デジタルチャネルでの問い合わせ比率30%削減という目標を達成し、コスト削減や業務効率化につなげています。
アダストリア
アパレルブランドを展開するアダストリアは、顧客への電話連絡の課題を解消するため、新たにSMSのチャネルを実装しました。
アダストリアは、全国に展開する1,300の店舗で顧客からの商品注文や取り置き、修理などの依頼を受け付けています。
さらに商品入荷や受け取り依頼の連絡を電話で行っていますが、電話がつながりにくいことで手間がかかったり、引き継ぎがうまくいかなかったりする課題を抱えていました。
そこで、全店舗にSMS配信の仕組みを導入し顧客への連絡をすべてSMSに切り替えることで、店舗スタッフによる電話連絡の時間が約80%減少しました。
また、頻発する再架電を避けられるようになり、店舗スタッフの心理的な負担軽減にもつながっています。
第一生命保険
第一生命保険は、2021年12月に新たな顧客接点として「ミラシル」というWebサイトを開設しました。
ミラシルでは、1,000万人を超える保険契約者の行動データをもとに、保障や資産形成、健康・医療などのパーソナライズ化された情報コンテンツを発信しています。
サイト上には専用フォームやチャット、電話などの相談窓口が設置されているため、情報を入手したユーザーが即座に相談や面談を行えるのが特徴です。
システム面では、CMS(コンテンツ管理システム)とCRMを連動させています。
第一生命保険はミラシルとは別に公式サイトを運営していますが、ユーザーと密接にコミュニケーションを行える顧客接点は数が限られていました。
今後はミラシルに順次コミュニケーション機能を追加し、利便性を高めようとしています。
東京ヤクルトスワローズ
東京ヤクルトスワローズは、新型コロナウイルスの感染拡大で来場者が減少し、ファンとの接点が弱まってしまう課題を抱えていました。
そこで、ECサイトを訪れる顧客の行動を把握できる分析ツールを導入します。
分析ツールから取得した顧客の属性や流入経路、ページ閲覧時間といったデータをもとに、ECサイトのグッズ販促を行うことで、ファン体験の改善と成果創出に着手しました。
この施策はグッズ販促だけではなく、チケット販売サイトやファンクラブサイトなど、ほかのデジタル接点でも活用できます。
例えば、2022年の新入団選手発表会では、ファンと双方向的なコミュニケーションを行えるようライブ配信システムを導入しました。
蓄積したデータを有効活用したデジタル接点強化の好事例だといえるでしょう。
まとめ:目的を明確にした上で顧客接点のデジタル化をはかろう
インターネットの普及や購買行動の変化により、デジタル接点を強化する重要性が高まっています。
多様化する顧客ニーズを的確に捉えるためにも、顧客接点をデジタル化し、チャネルごとに適切な施策を考える必要があります。
そのためには、まず目的を明確にすることが大切です。自社が定義する顧客との理想的な関係性をチーム全体で共有し、顧客情報をもとに戦略を構築しましょう。
戦略的に生み出された新たなデジタル接点は、顧客との良好な関係を築く架け橋となります。
カスタマーサクセス・カスタマーサポート専門会社アディッシュ株式会社では、今回ご紹介した顧客接点のデジタル化支援として、ツールの選定や導入支援などをご提供しております。
顧客接点のデジタル化に関するお悩みはぜひお問い合わせください!
顧客接点のデジタル化を相談!

この記事を書いたライター
山田理絵
不動産営業を経験後、アディッシュにて、カスタマーサクセス関連商材のインサイドセールスを担当し、初期接点から課題の顕在化をし機会創出を行う。 趣味はポールダンスと料理。